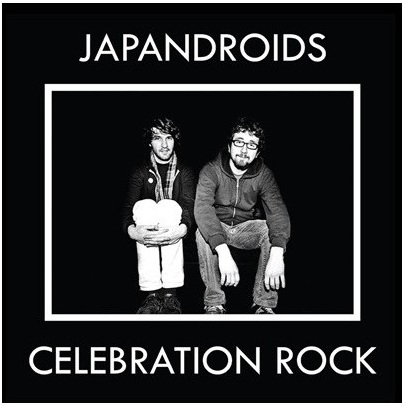|
ON TOUR (JAPAN) NEWS ABOUT ■Japandroidsについて 「まず言えるのは、僕にとってもデイヴにとっても、ジャパンドロイズは最初のバンドなんだ。自分達がプレイしたことのある唯一のバンドで、ロック・バンドとして一緒にプレイした相手もお互いしかいないんだよ。知り合ったのが10年くらい前、大学でだった。僕は高校の時の親友と一緒に、大学進学で(カナダの)ブリティッシュ・コロンビア州ヴィクトリアに引っ越して。で、その親友の近所にデイヴが住んでたんだよね。僕はしょっちゅう友達の家で過ごしてたから、それで彼を通じてデイヴと知り合ったんだ。結局みんな一緒につるむようになって……大学では僕らの友達はみんな音楽に共感してて、それが共通点だった。全員がバンドをやりたがってたわけじゃないけど、みんな音楽が大好きで、レコードやCDを集めて、ライヴに通ってて。僕とデイヴはそれで友達になったんだよ。一緒にライヴに行ったり、音楽の話をしたり。いいバンドが出てきたら、二人とも同じアルバムを買ってたし、ライヴがあったら行ってた。音楽が好きで、同じバンドを好きだってところで友情が育っていったんだ。それに二人とも、大学を通じてどんどん音楽ファンになっていって、レコード集めてライヴに行って音楽の話をして……唯一やってないのは、音楽をプレイすることだけだった。最後までやらなかったのがそれだったんだよね。当時の仲間の半分は、だんだん実際に音楽をプレイすることに興味を持って、バンドをやるようになった。あと僕にとっては、大学時代に初めて地元の音楽シーンっていうのを体験したんだ。同じ町に住んでる人がバンドをやってて、あちこちで見かけるっていう。有名なバンドとか、ツアー・バンドじゃなくてね。僕は小さな町で育ったから、地元の音楽シーンがなかった。だから子供の頃は、自分がバンドを始められるなんて思いもしなかったんだよ。僕が知ってたバンド、好きだったバンドはどれも有名なビッグ・バンドだったから。テレビやラジオや雑誌で知るようなバンドで、自分の町でライヴに出かけて、バンドを見ることもなかったし。自分でバンドを始めること自体、不可能みたいに思ってた。でも大学では、周りの人がバンドを始めて、自分でライヴを開いたりしてた。それで初めて、僕らは『僕らにもできるかもしれない』と思ったんだ。自分でも楽器を弾けるようになって、同じようにやれるかもしれない、って。それでデイヴと二人、大学を卒業したらバンクーバーに引っ越して、バンドを始めようって決めた。楽しむためにね。大学の頃からデイヴはドラムを練習してたし、僕は子供の頃からギターが弾けたんだ。でも、大学時代はずっとギターを持ってなくて。大学に入った時に手放したからね。だけど弾き方は知ってて……だからアイデアとしては、卒業の頃にはデイヴがドラムを叩けるようになって、僕がギターを買う、っていう。その後でバンクーバーで他のメンバーを見つけようと思ってた。そのつもりで僕らはバンクーバーに引っ越して、一緒にプレイしはじめたんだけど、一緒にやる他のメンバーがまったく見つからなくて。誰も僕らとはプレイしたがらなかったんだ。しばらくすると二人でかなりうまくプレイできるようになってきて……でも誰も僕らに加わろうとはしなかった。最後には僕ら、もう待ち切れなくなったんだよ。ライヴもやりたかったし、曲を書きたかったし、レコーディングもしたかったから。で、ある時点で、『二人でやろう』って決めた。最初にレコーディングした時は、二人だけで、ヴォーカルのないインストゥルメンタル・トラックを録ったんだ。それを人に聴かせて、ヴォーカルを探そうと思ってね。誰かに歌のパートを考えてもらおうって・・・・・・でも、僕らはそういう人が見つけられなかった。でも、僕もデイヴも歌いたくなかったし、歌詞を書いたこともなかったし。いい歌声を持ってるわけでもなかったし・・・・・・。僕らの初期のマテリアルを聴いてもらえばわかるんだけど、いやいや歌ってるシンガーの歌なんだよね。だからこそ、初期の曲には歌詞があんまりないんだ。同じ歌詞が延々繰り返されたり・・・・・・他にどうすればいいのかわからなくて。僕らがシンガーの役割を受け入れるのには、かなり時間がかかった。たぶん今回の新作は、僕らが初めて、『歌も重要なんだ』って認めた最初のアルバムじゃないかな。それを受け入れたっていう」 ■2ピースのバンド 「僕らは2ピースのバンドに聴こえたくなかった、ってこと。例えばホワイト・ストライプスは、2ピースのバンドに聴こえる。彼らはそう聴こえたがってるし、それが彼らの場合、すごくうまくいってる。でも、僕らは……ホワイト・ストライプスが嫌いなわけじゃないけど、『ホワイト・ストライプスみたいになりたい』ってバンドを始めたんじゃない。僕らはストゥージズやリプレイスメンツ、ローリング・ストーンズみたいになりたかったんだ。4人、5人のバンドの音を出したかったんだよ。つまり、僕らが時間をかけて作ってきた音楽スタイルは、『二人しかいなくても、もっと人がいるようなサウンド』を目指して、僕らは自分達の音楽スタイルを作ってきたんだ。でも他の2ピース・バンドはほとんど――ブラック・キーズにせよザ・キルズにせよ、デス・フロム・アバブだって――二人しかいないことを受け入れてる。彼らも曲も、二人しかいないように聴こえるしね。ホワイト・ストライプスの曲を聴くと、二人いるのが聴こえるよね? でも僕らのバンドを知らずに聴いたら、二人しかいないってことがわからないかもしれない」 ■『Celebration Rock』 「ファーストが出た後、僕らは2年近くツアーしたんだ。かなり長期間ツアーが続いた。あれだけライヴをやって、ツアーを続けたおかげで、僕らはそれぞれの楽器が上手くなっただけじゃなく、一緒にバンドとしてプレイするのもすごく上手くなったんだよ。今回はその部分を見せたかった。だからアルバムに対しては、特にテーマやコンセプトはなくて。『こういうのにするぞ』みたいな考えはなかったんだよね。ただファーストを作ってから何百回とライヴを重ねてたから、そこを見せつけてやろう、って感じだった。演奏も、バンドとして一緒にやることも、歌もこれだけすごくなったんだぞ、って。僕らの『ポスト・ナッシング』以前の初期の音源を集めた『ノー・シングルズ』を聴いてもらえばわかると思うんだけど、『ノー・シングルズ』から『ポスト・ナッシング』、それから今回の『セレブレイション・ロック』を聴いてもらえば、すごく自然に進化してるのがわかると思う。バンドが進化していってるのがね。別に技術的に違うことをやってるわけじゃない。僕らはどのアルバムも同じスタジオでレコーディングしたし、エンジニアも機材も同じだったし、方法も同じだった。ただバンドとして、曲を書くのが上手くなっていったし、二人一緒のプレイも上手くなっていった。すごく自然にね。3枚を一つのプレイリストに入れて、最初から最後まで聴いたら、ごく自然に、でも明らかによくなってるのがわかると思う」 ■サウンド 「僕はギターにシグナルを付けているんだ。だからギターは一本なんだけど、それがいくつものアンプに繋がっている。で、それぞれのアンプから違う音が出るようになっているんだ。ベースみたいな低音が出るのもあれば、高音になって出るアンプも、中音域になるアンプもあって。一本のギターを一つのアンプに繋ぐ代わりに、三つとか四つのアンプに繋げているから、三つ、四つの違うサウンドになって出てくるんだよ。だから実際にあるもの以上の音、厚みがあるように錯覚する。でもライヴの時と同じで、レコーディングの時も、ほとんどはギターが一本で、しかもワンテイクで録ったんだ。あと、アンプが複数台あるから、どのアンプの音量を上げて、どのアンプの音量を下げるかも調節できる。だから余計にギターが複数あるように聞こえるんだよ。厚みが出てくる。みんなが考えるよりずっとシンプルなんだ」 ■カヴァー 「日本盤には北米やヨーロッパでリリースした7インチを全部収録したんだ。僕は他のバンドをカヴァーしたバンドを通じて、好きなものをたくさん見つけていったんだ。子供の頃はガンズ・アンド・ローゼズやニルヴァーナを聴いてたんだけど、僕はガンズ・アンド・ローゼズによるカヴァーを通じて、ミスフィッツやストゥージズ、ボブ・ディランを発見した。パンク・ロックに熱中したのも、元はと言えばガンズ・アンド・ローゼズがパンク・バンドをたくさんカヴァーしてたからなんだ。デヴィッド・ボウイからピクシーズまで、ニルヴァーナもいろんな人をカヴァーしてただろ? 同じように僕はいろんなバンドをニルヴァーナを通じて知った。だからこそ僕らは自分達もカヴァーをやりたいと思ってるし、僕らのファンに同じ体験をしてほしいんだよ。オーディエンスがもう知ってるバンドをカヴァーしたって、意味がないよね? そうじゃなく、僕らのカヴァー曲を遡って、それまで知らなかったバンドを見つけ出す体験をしてほしい。その意味でビッグ・ブラックやX、ニック・ケイヴ、ザ・ガン・クラブをカヴァーしたのは、今ジャパンドロイズを聴いてる人が知らないんじゃないかと思ったからなんだ。そしたら僕らのリスナーがそういうバンドを発見して、好きになってくれるかもしれない」 ■ライヴ 「オーディエンスと相互的にやり取りがあればあるほど、いいライヴになるのは確かだね。観客がラウドであればあるほど、ライヴに熱中すればするほど、僕らも熱が入るし、いいプレイができる。お互いにどんどんよくなっていくんだよ。だから、観客には一緒に歌ってほしいし、好きなだけラウドになってほしい。そうすれば僕らも目一杯やるし、観客がワイルドになるほど、僕らもワイルドになれる。今はライヴの最後を“フォー・ザ・ラヴ・オブ・アイヴィ”で締めてるんだけど、やっぱりあのカヴァーが一番盛り上がるし、僕もやってて盛り上がる。あの曲をやる時には、それでライヴの最後だから、そこで自分に残ってるすべてのエナジーを吐き出す感じになるな」 |
|
|